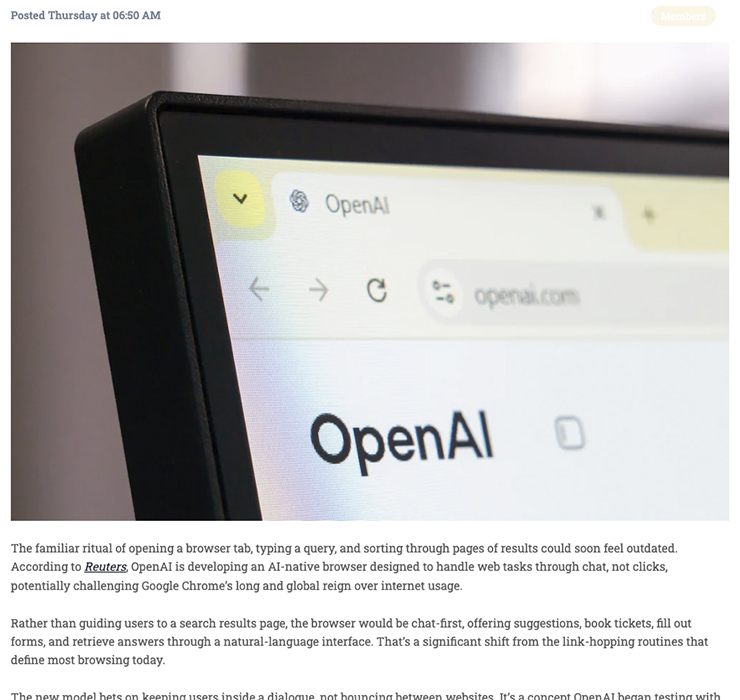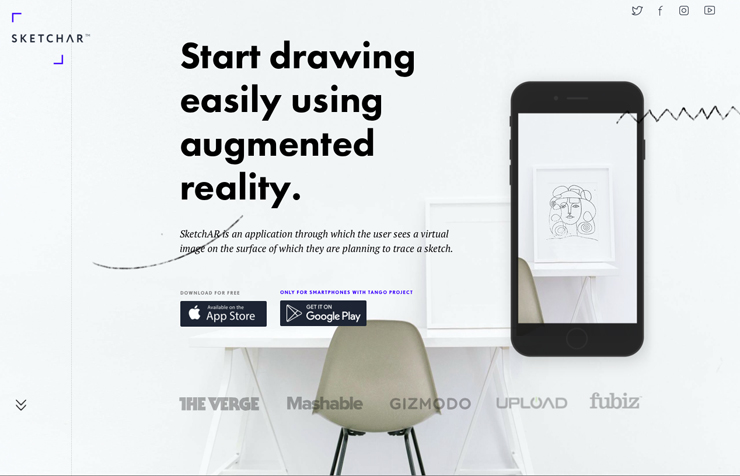結果がどうなるのか、おもしろい実験になりそうです。
「生産性が倍増する」という目標はなぜか昭和的な感じもしますが、AIに何を期待するのかという点で現実的な取り組みのような気がします。
個人の能力の拡大よりも、組織運営の無駄の削減にAIを使うのは、規模が大きい日本企業に向いてるかも。
以下は記事からの引用です。
「会議の要約や文書作成、経費管理、研究など、チームを遅らせるような反復的な作業を、これらのツールが担うことが期待されています。」
「AIは人間の努力の代替ではなく、支援ツールとして活用する意図です。」
「従業員は、手動でタスクに取り組む前にAIツールを活用するよう奨励されており、自動化をワークフローの不可欠な要素として位置付ける「AI優先」のアプローチが促進されています。」
「AIは必ずしも効率向上を保証するわけではありません。ある事例では、AIツールを使用する開発者が、自分たちはより速く働いていると信じていたにもかかわらず、タスクを完了する速度が遅かったことが示されています。」
うまくいくといいですね。
OpenAIからの正式な発表ではありませんが、やっぱりそうだよね・・・という感じです。
ベースはChromeやEdgeと同じChromiumだそうですが、見た目を変えたり機能を追加した程度のものではなさそうです。
「このブラウザは、ユーザーを検索結果ページに誘導するのではなく、チャットファーストで、自然言語インターフェースを通じて、提案、チケット予約、フォーム入力、答えの取得を提供する。これは、今日のほとんどのブラウジングを定義しているリンクホッピングのルーチンからの重要なシフトである。」
「日常的なウェブタスクを自動化するために設計されたOperatorツールをインターフェイスに組み込むことで、ボルトオンの拡張機能ではなく、摩擦のない統合を目指している。こうすることで、ブラウジングは受動的なナビゲーションから能動的でインテリジェントな「デリゲーション(委任)」へと進化する。」
だそうです。
デリゲーション(委任)という概念は新しい気がしました。
このブラウザが主流になれば、コンテンツやサービスとの信頼関係の持ち方が変わるので、WebのUIUXも変わる気がします。
WebのUIUXには視覚的な要素は無駄になるのかも。
OpenAI is reportedly building its own browser to take on Google Chrome >>
Studio Ghibli-inspired memes and portraits made with ChatGPT are flooding the internet
The trend emerged after OpenAI released its new images feature in GPT-4o. pic.twitter.com/Ssq1IUEDkg
— Sportskeeda Anime (@Anime_SKD) March 27, 2025
GPT-4oモデルがリリースされた直後から爆発的にSNSにアップされました。
サム・アルトマンが「GPUが溶けている」というくらいです。
とても楽しい画像ツールですが、基になったデータに対しての許可、クレジット、報酬なしにスタイルを模倣するサービスで収益を得ることに疑問もあるようです。
いろいろAIツールがあっても、その生成物は個人のSNS以外には使いどころがないような気もします。一方で、AIツールとしては個人のSNSで広く使われれば大成功かも。
OpenAI’s ChatGPT sparks viral Studio Ghibli-style art craze as copyright storm looms >>
デザイナーが描いたスケッチを元にして、AIで空力性能、シャシー寸法、室内寸法の条件でスケッチのバリエーションを生成してます。生成されたスケッチを元にして、さらにデザイナーが手を加えていくプロセスのようです。
「デザインプロセスを補助する」という役割で有用な気がします。むしろ、好きな形を描いちゃうデザイナーに必要な要件を守らせるAIツールなのかも。現在のデザイナーに必要なのは、こういうツールのような気もしてきます。
要件の多い分野のデザインにこそAIが威力を発揮するようになるなら、デザイナーは考える必要が少なくなっていくかも。
Toyota Creates Text-To-Render Tool To Help Designers Conjure Up Future EVs >>
たのしいプレゼンができそう。
カメラを通して身体の部位のジェスチャーとグラフィック要素を連携させることができるようです。
ネット会議とかYouTuberが使うことを想定しているのでしょうか。
使い方も簡単そうですが、本当にプレゼンで使うには心理的なハードルが高そう。
遊びで使うのはおもしろそう。
MITとAdobe、グラフィカルオブジェクトを手などでリアルタイム操作できるARプレゼンテーション作成ツールを発表 | Seamless >>
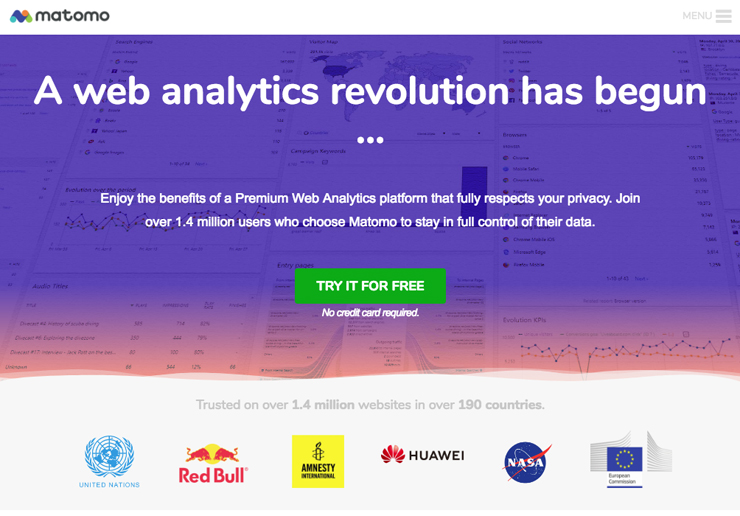
海外では、ヨーロッパのGDPRにふさわしい分析方針が求められているようです。
「私は、個人データではなく集約データが必要だという結論に達しました。それは行われた行動の合計を追跡しますが、人については何もしません。」
「人、訪問者、またはブラウザのユーザーは、追跡されたくないと言うことができるはずです」
「Google がGoogle Analyticsをリリースしたとき、世界の一定の割合が同じテクノロジを望んでいるが、集中型の企業から提供されていない分散型のテクノロジであることが望ましいことは明らかでした」
国連、アムネスティ、NASA、欧州委員会、そしてその他約150万のWebサイトがMatomoを使用しているそうで、MatomoはGoogle Analyticsの約95%のことができるそうです。
オープンソースの分析プラットフォームの一部は有料サービスのようですが、無料の分析が無責任な振る舞いをしてるなら有料も検討すべきなのかも。
サイト分析で個別ユーザーの行動を細かく知りたいという考え方は昔の顧客管理システムから来ているのかも。
WEBの場合はユーザーを個別に追いかけるのではなくて、別の視点がある気がします。
ひさしぶりにスマホを買い替えようとしてますが、iPhoneXSってすごい。
比較機種は EOS C200 のようです。
EOSのほうが階調が肉眼に近いようです。
どこかのホテルでの展示会ではじめてFlashのデモを見たとき、当時すでにあったDirectorと何が違うのか理解できませんでした。
Flashの大流行はウェブにエンターテイメント要素を持ち込んでくれました。いまでも思い出せるくらい楽しいコンテンツもあります。
ただし(自戒を込めて)Flashでの制作は継ぎはぎだらけのヒドいコードやスクリプトになる場合がありました。
Flashが悪く言われるようになった原因には、制作者の技術不足やいい加減さもあったように思います。
Flashはいろいろな点で歪んだものだった気がしますが、それゆえに無理や無茶をやる余地があり創造的な試行錯誤ができました。その状況はいまのウェブよりも自由で創造性があったのかも。
くわしくは…
アドビの「Flash」、今度こそ本当に終了──おかげでウェブはもっと安全で軽くなる | WIRED
MK12とかは好きでした。
http://mk12.com/MKXII/work/
これはおもしろそう。最近読んでるホックニーの『絵画の歴史 洞窟壁画からiPadまで』のなかにも画家が16世紀頃から光学的な投影を利用して絵画を制作していたことが紹介されています。(この本はかなりおもしろいです。)
このアプリもその歴史の延長線上にあるでしょう。ただし『絵画の歴史』にも「道具を理解しても、創作の秘密は明らかにならない。」とありました。
壁に描くには Android Tango のデバイスが必要なのかも。
Google Tango についてはこちら >>
MOLESKINEは以前から紙の上の手描きをスムーズにデジタルデータにする取り組みをしてましたが、ついに紙に手描きをリアルタイムでタブレットやスマホにデジタルに記録できるようになったようです。$199.00で販売中。
使い方はこちら
ノートではなくてペンとアプリによる機能のようですが、それでもいいです。
くわしくはこちら
MOLESKINE – Smart Writing Set
© 2025 DESIGNERS UNION | ご自由に投稿できます。 お気軽にご利用ください。