
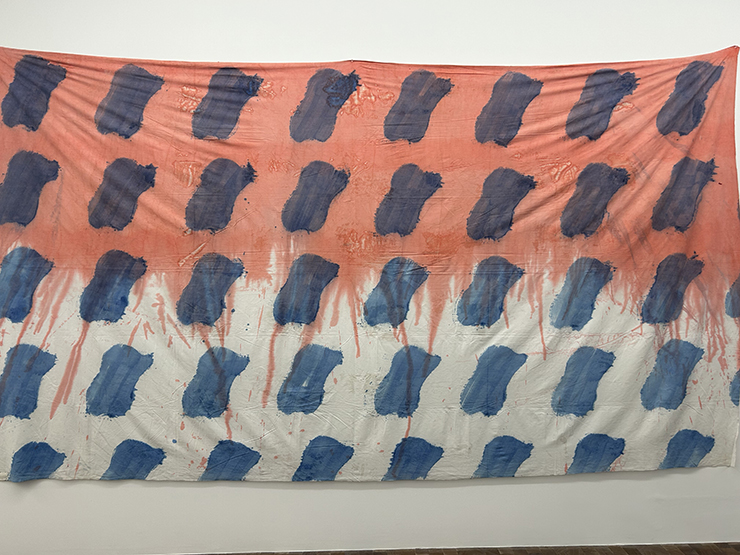


1970年代のフランスの前衛的な芸術運動で、90年代に世界各地で回顧展もあったそうです。
フランスの現代美術ギャラリーのCeysson & Bénétière(セイソン&ベネティエール)が東京・銀座にをオープン。そのオープニング展で作品が展示されています。
言葉の意味は「支持体/表面」で、「絵画の構造を解体する」というコンセプトです。
支持体としてのフレームと表面としてのキャンバスや顔料が解体されたモノとして展示されています。
コンセプトがどのように解釈されて、どのように展開されて、どのように作品として成立しているかを考えて見ると、とても楽しい展示です。
同じフランス語の「タブロー」の意味から広げて考えると、壁画から始まる絵画の歴史全体と繋がるコンセプトになるのかも。
個人的に昔からお気に入りのコンセプトで、21世紀の現在に置き換えてもメッセージ性を持ち得る気がします。
プロジェクションマッピングなどが洞窟壁画や教会の天井画で、このブラウザで見る物がタブローだったら、データ、コード、演算、表示などに解体され得るのかも。
サム・アルトマンが共同設立した新興企業「Tools for Humanity」の「World」というブランドの「Orb」と言うデバイスは、網膜スキャンを使ってユーザーを人間として認証し、デジタル認証コードを提供します。「これが本当に機能すれば、世界の基本的なインフラになる」とのことで、最近になって米国で登録が始まったそうです。
日本では数年前から各地でOrbが設置されて登録した人も多くいると思います。
CMを手掛けたのはBBDO New Yorkだそうです。
「World」が目指すゴールはとても明確ですが、前例のないサービスとブランドのCMを作る難しさは容易に想像できます。おなじみの曲で古き良き広告のスタイルのCMにしたのは正しい選択のように思います。
BBDO New Yorkのエグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクターによれば、
「これは製品のデモではない。人格テストなのだ。アルトマンが言うように、これが世界の基本的なインフラになるのなら、Worldブランドはそれが何者であり、なぜ私たちがそれを信頼すべきなのかを語っているのだ。親しみやすく、威嚇的でなく、どこか刺激的で、そう、楽観的でなければならない。すべての広告においてトーンは重要だが、AIがもたらす実存的な不安定さという文脈においてはなおさらだ。」
さらに、このCMの監督によれば、
「長くクルマの広告に携わってきましたが、人とクルマの間のインタラクションはいつも重要です。ここでは、Orbとのインタラクションがどのように行われるのか、スケールがわかるように考え抜きました。人間との比較でそのスケールを見せる必要があり、彼女の視線は少し下を向いています。」
とのことで、細心の注意を払った演出になっていることがわかります。
前例のないサービスとブランドの広告に、クルマという誰もが知ってる製品の広告を手掛けてきた監督を起用する視点も、さすがです。
以前はWeb3の文脈の中にあったサービスように認識していましたが、今ではAIと一対になったサービスとしてのポジションになって、それが受け入れられつつあるようです。
個人的には、Web3が描いたような未来が実現されたらいいと思ってます。
00年代のウェブのUIデザインを思い出します。
ずっと昔にWindowsのOSでも見たような気がしますが、それよりもずっと洗練されていると思います。
下層レイヤーの明度やコントラストを判断して、透明度やドロップシャドウが変化するようです。これはよくできた基盤になってる気がします。
アイコンの表示色や輪郭線を選択できるようですが、この自由度はデザイン言語の一貫性がなくなりそうな気もします。
使い慣れると良いのかもしれませんが、振舞いも視覚的にも騒がしい座布団といった印象です。
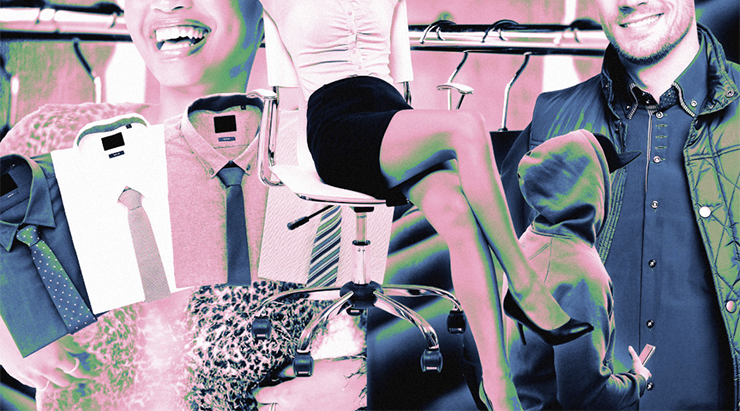
2000年前後に生まれたZ世代は、大学生から社会人になる頃にコロナ流行でのリモートワークを経験している世代になります。
オフィスで何を着ているのか、どうやってそれを見つけたのかを、様々な業界のZ世代に聞いてみた記事です。
この世代はオフィスでの服装についてこれまでの世代とは違った感覚を持ってるようです。
ファッションブランドにとっては、大きなチャンスになりそうな気もします。
以下は抜粋です。
「Z世代は、他の新入社員と同じような経験を積んだかもしれないが、職場復帰の義務化は、Z世代がオフィスの服装という1つの大きな教訓を逃したことを証明している。」
「ヴォーグ誌の言う『ビジネスカジュアルは死んだ』のような曖昧なドレスコードや、『オフィスサイレン』のようなセクシーなオフィスウェアのトレンドが氾濫し、Z世代は混乱したまま社会に出ている。」
「ドレスコードは『カジュアル』で従業員は『自分の判断で服装を選択することが期待される』と記載されています。不安の中、初日は過度にフォーマルな服装をすることにしました。・・・しかし、現実には制服があり、服装の基準がある。それは形式的なレベルに基づくものではありません。あるグループに属するというレベルに基づいているのです。」
「若いプロフェッショナルたちは、文書に書かれたガイドラインからではなく、周りの人たちの服装を真似ることによって、何を着るべきかを学び、徐々にお決まりの服装を作り上げていった。」
「私はZ世代に、ペダルを床まで踏み込むことを提案したい。皆さんはプレイブックを書き換えているのです。プレイブックはCOVIDで終わり、私たちは美を定義し、文化を創造する新たな機会を得たのです。」
引用元の記事は米国での話のようですが日本でも似たように感じます。
Z世代は帰属意識や仲間意識が強く、周囲を観察して何を着るべきかを判断して、素早く適切に順応する世代だと思います。
しかもその過程で、帰属するコミュニティの中での自分のポジションと、どうしたら優位になれるのかを判断できるようです。
Z世代のこの感覚は素晴らしいと思っていますが、これにはSNSのアルゴリズムによる同質化という側面も感じます。
最近、個人的にも服装のギャップを感じることがあり、この記事はとても刺さるものがありました。
これからZ世代がオフィスの風景と企業文化を塗り替えていくのかも。彼らから見て威圧的な印象にならないようにしたいです。
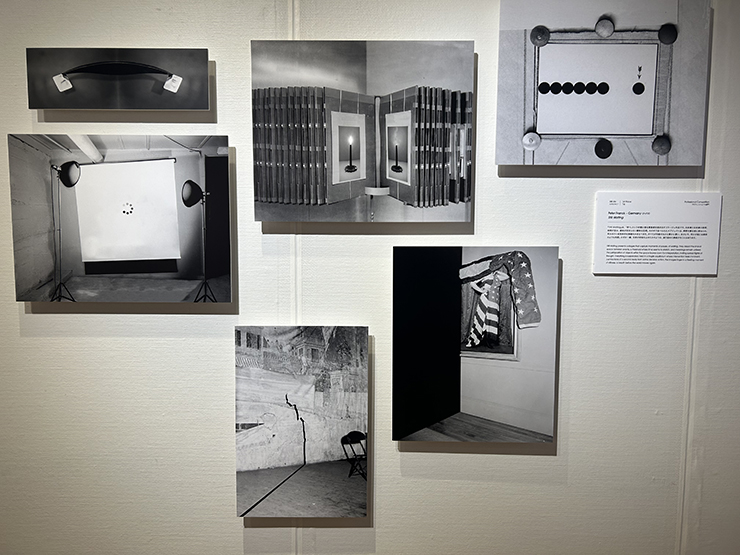

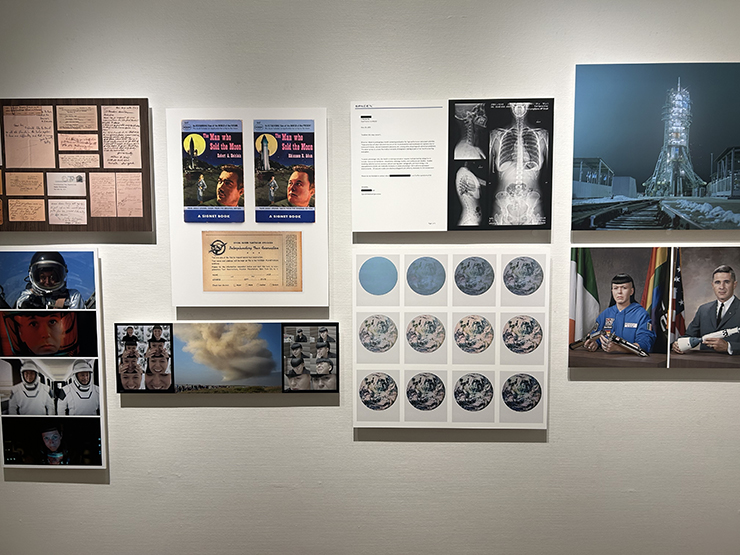
社会派なテーマを扱った連作の展示になっていて見応えありました。
作品のコンセプトについての短くわかりやすいテキストが面白かったです。
もっと大きなサイズで、もっと良いプリントだったら、もっと違って見えたかもです。
ひさしぶりに銀座に行ったら、多くのビルが建て替わっていて、記憶と違う風景になってた。
© 2026 DESIGNERS UNION | ご自由に投稿できます。 お気軽にご利用ください。
